ADHDで同じ曲を聴く理由とは?発達障害との関係を解説

ADHDと同じ曲を何度も聴く行動の理由について、疑問に思ったことはありませんか。頭の中で音楽が流れる発達障害の特性なのか、それとも同じ曲を何度も聞くのは病気ですか?という不安を感じる方もいるでしょう。また、ADHDの人は同じことを何度も言いますか?といった反復行動や、ADHDの人は音が苦手ですか?という聴覚の特性も関連するかもしれません。
この記事では、同じ曲を何度も聞くasdとの違いは何か、同じ曲を聞き続けると脳が縮小するのかという噂の真相にも触れます。さらに、ADHDと同じ曲の問題に関連する心理や状態として、同じ曲を何度も聞く性格的な背景や、うつ病との関連、hspとの関係性、そして同じ曲を何度も聞くストレスの原因まで掘り下げ、ADHDと同じ曲の関連性のまとめとして分かりやすく解説します。
- ADHDで同じ曲を聴いてしまう具体的な理由
- ASDやHSPなど他の特性との関連性や違い
- 「脳が縮小する」といった噂の科学的根拠
- 行動の背景にある心理やストレスとの向き合い方
ADHDと同じ曲|何度も聴く行動の理由
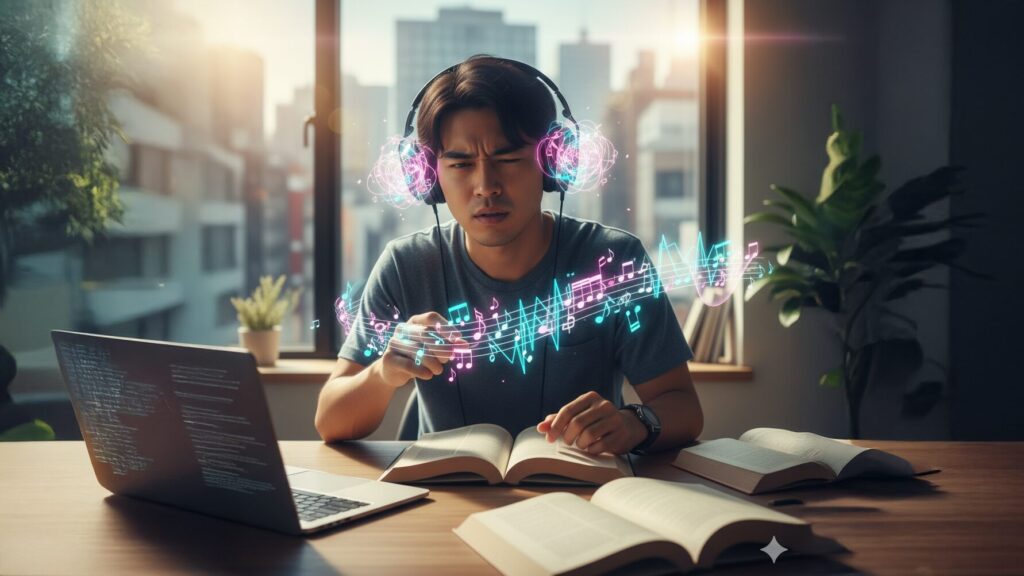
- 頭の中で音楽が流れる発達障害の特性
- 同じ曲を何度も聞くのは病気ですか?
- ADHDの人は同じことを何度も言いますか?
- ADHDの人は音が苦手ですか?
- 同じ曲を何度も聞くasdとの違いは?
- 同じ曲を聞き続けると脳が縮小する?
頭の中で音楽が流れる発達障害の特性
ADHDの当事者が「頭の中で同じ曲がずっと鳴り止まない」と感じる現象は、「イヤーワーム(earworm)」や「不随意音楽想起(Involuntary Musical Imagery)」として知られるものと深く関連している可能性があります。この現象は人口の90%以上が経験すると言われており、それ自体は異常ではありません。しかし、ADHDの特性によって、その体験がより頻繁で、コントロールが難しく、苦痛を伴うものに変わることがあります。
ADHDの脳は、思考や注意を司る前頭前野の働きに偏りがあるとされ、これが「脳内多動」と呼ばれる、常に頭の中が騒がしい状態を生み出します。このため、一度聴覚野にインプットされた音楽の断片が、本人の意思とは無関係に、まるで壊れたレコードのように自動再生され続けてしまうのです。
定型発達の人の場合、イヤーワームが起きても「ああ、またあの曲が流れているな」と客観的に認識し、他の思考に注意を向けることで自然に消えることが多いです。しかし、ADHDの特性を持つ人にとっては、好き嫌いに関わらず特定のフレーズが脳のワーキングメモリ(短期記憶)を占領し続け、他の作業への集中を著しく妨げてしまうという、より深刻な困難につながることが少なくありません。
イヤーワームはなぜ起こる?
イヤーワームの明確なメカニズムは完全には解明されていませんが、記憶と感情が密接に結びついていることや、脳が「未完了のタスク」を記憶しやすい(ツァイガルニク効果)ことなどが関係していると考えられています。曲の途中で聴くのをやめると、脳がその曲を「完成」させようとして、何度もループ再生してしまうという説もあります。
同じ曲を何度も聞くのは病気ですか?

結論から申し上げますと、同じ曲を何度も熱心に聴く行動自体は、医学的な意味での「病気」ではありません。むしろ、これはADHDや自閉スペクトラム症(ASD)といった発達障害の特性に根差した、脳機能に起因する行動の一つとして理解するのが適切です。
この行動の背景には、主に自己の内的状態を調整するための、合理的ともいえる理由が存在します。
1. 自己刺激行動(スティミング)としての役割
一定の心地よいリズムや予測可能なメロディーを持つ音楽を繰り返し聴くことは、脳、特に報酬系にとって安定した刺激となります。これは「スティミング(Stimming)」とも呼ばれる自己刺激行動の一種です。
周囲の環境が情報過多で混乱している時や、逆に刺激が少なすぎて退屈な時に、自分が完全にコントロールできる聴覚情報を脳に与えることで、精神的な安定を得たり、集中力を喚起したりする目的があります。
2. 認知的負荷の軽減と安心感の確保
発達障害の特性として、予期せぬ変化や新しい情報への対応を苦手とすることがあります。新しい曲を聴くという行為は、次にどんなメロディーが来るか、どんなリズムに変わるかを予測し続ける必要があり、脳にとっては少なからず「認知的負荷」がかかります。
一方、聴き慣れた好きな曲は、その展開が完全に予測できるため、脳は情報処理の負担から解放され、非常にリラックスした状態、つまり安心感を得ることができるのです。
このように、一見すると奇妙に映るかもしれないこの行動は、病的な症状などではなく、脳の特性に合わせて自分自身を最適な状態に保つための、当事者なりの無意識的かつ巧みな工夫と捉えることができるのです。
ADHDの人は同じことを何度も言いますか?

はい、ADHDの特性を持つ人の中には、会話の中で同じことを何度も質問したり、同じエピソードを繰り返し話したりする傾向が見られることがあります。この行動は、同じ曲を聴き続けることと同様に、ADHDの根本的な特性と関連していると考えられます。
この背景には、主に以下のような神経心理学的な要因が影響しています。
| ADHDの特性 | 具体的な影響 |
|---|---|
| ワーキングメモリの課題 | 短期的な情報を記憶し、同時に処理するワーキングメモリの機能に困難があるため、自分が数分前に話した内容や質問した事実を忘れてしまい、悪気なく再度同じことを言ってしまうことがあります。 |
| 実行機能の不全 | 思考を整理し、順序立てて話すといった実行機能の課題から、話がまとまらず、特に重要だと感じている核心部分を何度も口に出すことで、自分の考えを整理しようとすることがあります。 |
| 衝動性と不安 | 考えがまとまる前に口に出してしまう衝動性に加え、相手に正しく伝わっているか、自分が正しく理解できているかという不安から、確認のために何度も同じ質問を繰り返すことがあります。 |
このように、音楽の反復が主に聴覚的な自己刺激や安心感を求める行動であるのに対し、発言の反復は、主に脳内の情報処理、記憶、そして感情調整の特性から生じる行動と言えるでしょう。どちらもADHDの脳のユニークな働き方が深く関係しており、本人にとっては意図的でない場合がほとんどです。
ADHDの人は音が苦手ですか?

「ADHDの人は音が苦手」と一言で断定することはできませんが、多くの当事者が音に対して特有の困難さ、すなわち「感覚過敏」、特に「聴覚過敏」を抱えていることが、さまざまな研究で指摘されています。(参照:厚生労働省「発達障害」)
聴覚過敏とは、多くの人が気にも留めないような日常的な音、例えば冷蔵庫のモーター音、蛍光灯の点灯音、遠くで鳴っているサイレン、隣の部屋の話し声などを、耐えがたいほどの騒音として感じてしまう状態です。これらの音が必要な情報(例えば、目の前の人との会話)に割り込んでくるため、日常生活のあらゆる場面で集中することが極めて困難になります。
しかし、非常に興味深いことに、この聴覚過敏があるからこそ、特定の音楽、特に自分が選んだ「安全な」音楽に対しては、非常に強い安心感を覚えるという逆の側面も持ち合わせているのです。
周囲の予測不能で無秩序な雑音は、脳にとって大きなストレス源となります。それに対して、自分が選んだ好きな曲は、メロディーもリズムも完全に予測可能で、心地よく、安心できる音の世界を提供してくれます。つまり、ヘッドフォンなどで好きな曲を繰り返し聴く行動は、不快な外部の音情報を能動的に遮断し、自分の精神を守るための「音のバリア」や「聴覚の安全基地」としての重要な意味合いを持っているのです。
同じ曲を何度も聞くasdとの違いは?

同じ曲を何度も聴くという行動は、ADHDだけでなく、自閉スペクトラム症(ASD)の当事者にも非常によく見られる共通の特性です。しかし、その行動を駆動している内的なメカニズムや主な目的は、それぞれの障害のコアな特性によって異なると考えられています。
ADHDとASDにおける行動の背景的な違いを、以下の表にまとめました。
| 特性 | ADHD(注意欠如・多動症)の場合 | ASD(自閉スペクトラム症)の場合 |
|---|---|---|
| 行動の主な理由 | 不足しがちなドーパミンを補い、脳の覚醒レベルを調整する(自己刺激)目的や、注意散漫な状態から特定の作業に集中するための道具(集中ツール)としての側面が強いです。 | 常同行動(こだわり)の一環であり、世界の同一性を維持し、変化というストレスを避けることで強い安心感を得る目的が非常に強いです。 |
| 音楽の選択傾向 | その時の気分やタスクの内容に応じて、脳を活性化させたい時はアップテンポな曲、落ち着きたい時は静かな曲など、聴く曲が比較的変わりやすい傾向があります。 | 特定のアーティスト、特定のアルバム、あるいは特定の1曲そのものへの強い愛着やこだわりがあり、数ヶ月から数年単位で同じ曲を聴き続けることも珍しくありません。 |
| 根底にある特性 | 報酬系の機能不全、衝動性、注意のコントロールの難しさが深く関係しています。 | 強い感覚過敏性や、同一性への強い希求、パターン化された行動への固執が深く関係しています。 |
もちろん、これはあくまで典型的な傾向を比較したものであり、ADHDとASDの両方の特性を併せ持つ(併存する)人も多いため、個人差が非常に大きいことを理解しておく必要があります。しかし、大まかな違いとして、ADHDは「脳の状態を調整するための能動的なツール」として、ASDは「変わらない世界を確認するための受動的な儀式」として同じ曲を聴く傾向がある、と考えると理解の一助になるでしょう。
同じ曲を聞き続けると脳が縮小する?

「同じ曲を聴き続けると脳が縮小する、あるいは機能が低下する」という話を耳にして、不安に感じたことがあるかもしれませんが、現時点でそのような主張を直接的に裏付ける、信頼できる科学的根拠は存在しません。これは、脳の働きに関する知識が単純化されて広まった、一種の誤解や都市伝説と考えるのが妥当です。
確かに、私たちの脳は「ニューロプラスティシティ(神経可塑性)」という性質を持ち、新しい経験や学習によって常に変化しています。そのため、普段聴かないジャンルの音楽に触れたり、複雑な構成の曲を聴き込んだりすることは、脳の様々な領域を刺激し、認知機能にとって有益な効果をもたらすと考えられています。
その観点から見ると、毎日同じ曲ばかりを聴いていると、脳はその音響パターンに完全に慣れてしまい、情報処理が自動化・省エネ化される可能性はあります。しかし、これは「脳の活動が効率化される」ということであり、脳の神経細胞が死滅して物理的に萎縮したり、記憶力や思考力といった基本的な機能が著しく低下したりすることを意味するものでは全くありません。
むしろ重要な脳の働き
音楽を聴くと、快感や意欲に関わるドーパミンや、精神の安定に関わるセロトニンといった神経伝達物質が分泌されます。この効果は、たとえ聴き慣れた曲であっても期待できるものです。特に発達障害のある方にとっては、安心感を得て精神を安定させるという重要な役割を担っています。脳の縮小という根拠のない心配をするよりも、音楽がもたらすポジティブな効果を大切にする方が、はるかに建設的と言えるでしょう。
「ADHDと同じ曲」関連する心理や状態

- 同じ曲を何度も聞く性格的な背景
- 同じ曲を何度も聞くうつ病との関連
- 同じ曲を何度も聞くhspとの関係性
- 同じ曲を何度も聞くストレスの原因
- ADHDと同じ曲の関連性のまとめ
同じ曲を何度も聞く性格的な背景
発達障害の特性という側面とは別に、同じ曲を何度も聴く行動の裏には、その人が置かれた心理状態を無意識的に調整しようとする心の働きが深く関わっていることがあります。このメカニズムは、音楽療法などの分野で「同質の原理(Iso-Principle)」として知られています。
同質の原理とは、自分の現在の感情(気分)と同じような雰囲気や曲調を持つ音楽に触れることで、その感情が音楽によって肯定され、結果的に感情が浄化(カタルシス)されて心が安定に向かうという考え方です。例えば、失恋して深く落ち込んでいる時に、無理にアップテンポで明るい曲を聴いても、かえって自分の気持ちとのギャップに苦しんでしまいます。むしろ、静かで悲しいバラードを聴くことで、「この曲は自分の気持ちを分かってくれる」と感じ、涙と共に悲しみが解放され、心が軽くなることがあります。
この原理に基づくと、特定の同じ曲を繰り返し聴いている場合、その人はその曲が表現している感情のトーン(激しい怒り、静かな悲しみ、穏やかな喜びなど)と自分自身の心理状態を同調させ、心のバランスを回復しようとしていると考えられます。特に歌詞のある曲を好んでリピートしている場合は、その歌詞が、普段は言葉にできない自分の内なる想いや葛藤を代弁してくれている、という側面も強く影響していることでしょう。
同じ曲を何度も聞くうつ病との関連

同じ曲を何度も繰り返し聴くという行動は、うつ病や、それに近い抑うつ状態にある人々にも顕著に見られることがあります。これは、精神的な活動エネルギーが著しく低下している状態と密接に関係しています。
世界保健機関(WHO)によると、うつ病の中心的な症状には、持続的な気分の落ち込みに加えて、興味や喜びの喪失(アンヘドニア)が挙げられます。このような状態では、新しい音楽を探したり、未知のアーティストを開拓したりするような、能動的な行為そのものが非常に大きな精神的負担となってしまいます。そのため、脳にとって処理が容易で、かつ安全であることが分かっている聴き慣れた曲に繰り返し触れることで、最低限の精神的な刺激と安心感を得ようとするのです。
反芻思考との関連
また、うつ病の際に特徴的な、ネガティブな考えが自分の意思とは関係なく頭の中をぐるぐると回り続ける「反芻思考」と、同じ曲が頭から離れないイヤーワーム現象が結びつくこともあります。特に、絶望感や悲しみを歌った暗い曲調の音楽を、何週間、何ヶ月にもわたって延々と聴き続けている場合は、本人のつらい心理状態が強く反映されている可能性があり、単なる音楽の好みとして看過できない、注意が必要なサインとも言えるでしょう。
同じ曲を何度も聞くhspとの関係性

HSP(Highly Sensitive Person)は、病気や障害の名称ではなく、生まれつき外部からの刺激に対して非常に感受性が強く、繊細な気質を持つ人々のことを指す概念です。このHSPの気質を持つ人もまた、同じ曲を繰り返し聴く傾向が強いことが知られています。
HSPの人は、神経システムが些細な刺激をより深く処理するため、人混みの喧騒、突然の大きな音、複数の人が同時に話す声、あるいは強い光や匂いなど、多くの感覚情報によって容易に圧倒されてしまいます。その結果、人よりも早く精神的なエネルギーを消耗し、疲れ果ててしまうのです。そのため、意識的に外部からの刺激を遮断し、自分の内面をリセットさせるための「ダウンタイム」が不可欠となります。
この点で、ヘッドフォンやイヤホンで好きな音楽を聴くという行為は、HSPにとって極めて有効な自己防衛策となります。特に、展開が完全に予測できる聴き慣れた同じ曲は、外部の予測不能でカオスな刺激から自分を隔離するための、安全で快適な「音のシェルター」のような役割を完璧に果たしてくれるのです。ADHDの聴覚過敏への対処と似ていますが、HSPの場合はより気質的な「過剰な刺激からの戦略的撤退」という意味合いが強いと言えるでしょう。
同じ曲を何度も聞くストレスの原因

同じ曲を何度も聴く行動は、本人にとっては精神の安定や集中に欠かせない重要な手段であることが多いですが、その一方で、意図せず本人や周囲の人々のストレスの原因となってしまうという、二面性も持っています。
1. 当事者本人が感じるストレス
最も代表的なストレス源は、自分の意思でコントロールできない「イヤーワーム」です。静かに本を読みたい時や、重要な会議に集中しなければならない場面で、頭の中に特定の音楽が大音量で鳴り響き、思考を妨げられてしまうと、大きな不快感や焦燥感を感じます。これは、特にADHDの特性を持つ人が日常的に経験しやすい困難の一つであり、パフォーマンスの低下に直結します。
2. 周囲の人々が感じるストレス
一方で、家族や職場の同僚、友人など、その人の周りにいる人々がストレスを感じるケースも少なくありません。例えば、オフィス内で同じ鼻歌を無意識に一日中歌い続けていたり、家庭のリビングでスピーカーから同じアルバムが延々と流れていたりすると、聴いている側は飽きや不快感を覚え、「もうその曲は聴きたくない」と感じてしまうかもしれません。これが原因で、人間関係に不要な摩擦が生じる可能性も考えられます。
お互いのためのコミュニケーション
もし周りの人の音楽を聴く行動が気になった場合、その行動を頭ごなしに「おかしい」「迷惑だ」と否定するのは避けましょう。前述の通り、本人にとっては自己調整のための生命線ともいえる行動かもしれません。「何か理由があるのかな?」と背景を想像し、「もしよかったらイヤホンを使ってみない?」と提案するなど、お互いが快適に過ごせる妥協点や解決策を一緒に考えるという、思いやりのあるコミュニケーションが非常に大切です。
ADHDと同じ曲の関連性のまとめ
この記事では、ADHDの人が同じ曲を聴く理由について、その背景にある神経学的な特性から、関連する心理状態まで、多角的に詳しく解説しました。この行動は単純な「癖」ではなく、多くの場合、当事者なりの合理的な理由に基づいています。最後に、記事全体の重要な要点をリスト形式で改めて振り返ります。
- ADHDで同じ曲を聴くのは病気ではなく脳の特性に関連した行動である
- 意思に反して音楽が鳴り続けるイヤーワームは脳内多動と関係が深い
- 心地よい刺激で脳を調整する自己刺激行動(スティミング)の一種
- 聴覚過敏がある場合、不快な外部音を遮断する防衛策でもある
- ASDの「こだわり」とは行動の背景にある主な目的が少し異なる
- 同じ曲を聴き続けても脳が縮小するという科学的な根拠は存在しない
- 心理的には自分の感情と曲調を合わせ心を整える同質の原理が働く
- うつ病の際はエネルギー低下により新しい刺激を避け同じ曲を好みやすい
- HSPの人は過剰な外部刺激から身を守るシェルターとして音楽を使う
- コントロール不能なイヤーワームは当事者にとって大きなストレスになり得る
- 周囲の人は行動を否定せず背景を理解しコミュニケーションを図ることが大切
- 反復行動は音楽だけでなく発言や動作など他の形で見られることもある
- 聴き慣れた曲は脳にとって認知的負荷が少なく安心できる安全基地である
- 一見不思議な行動も脳の特性に合わせた無意識的で合理的な工夫といえる
- 行動の背景を正しく理解することが当事者と周囲双方の過ごしやすさに繋がる






