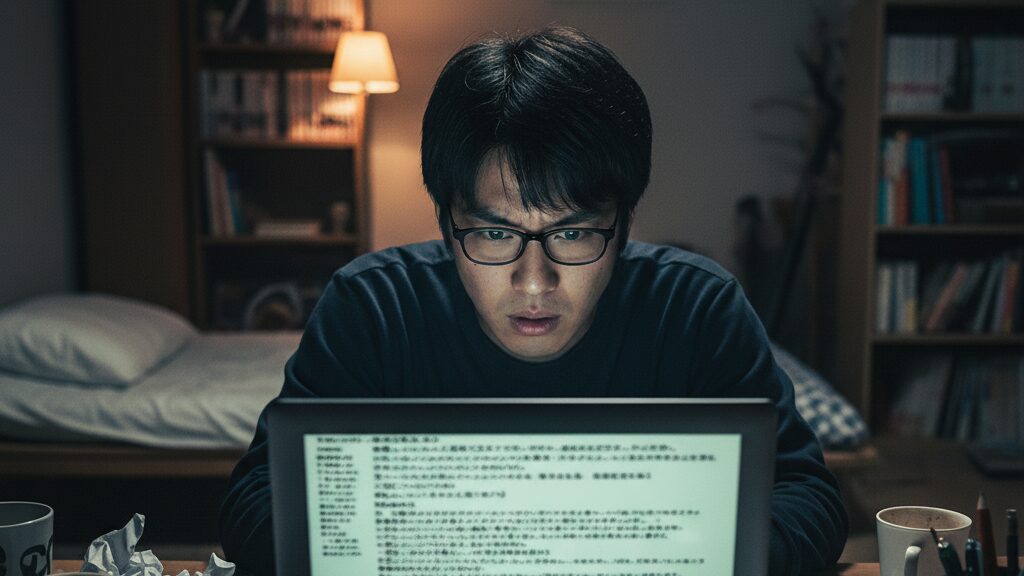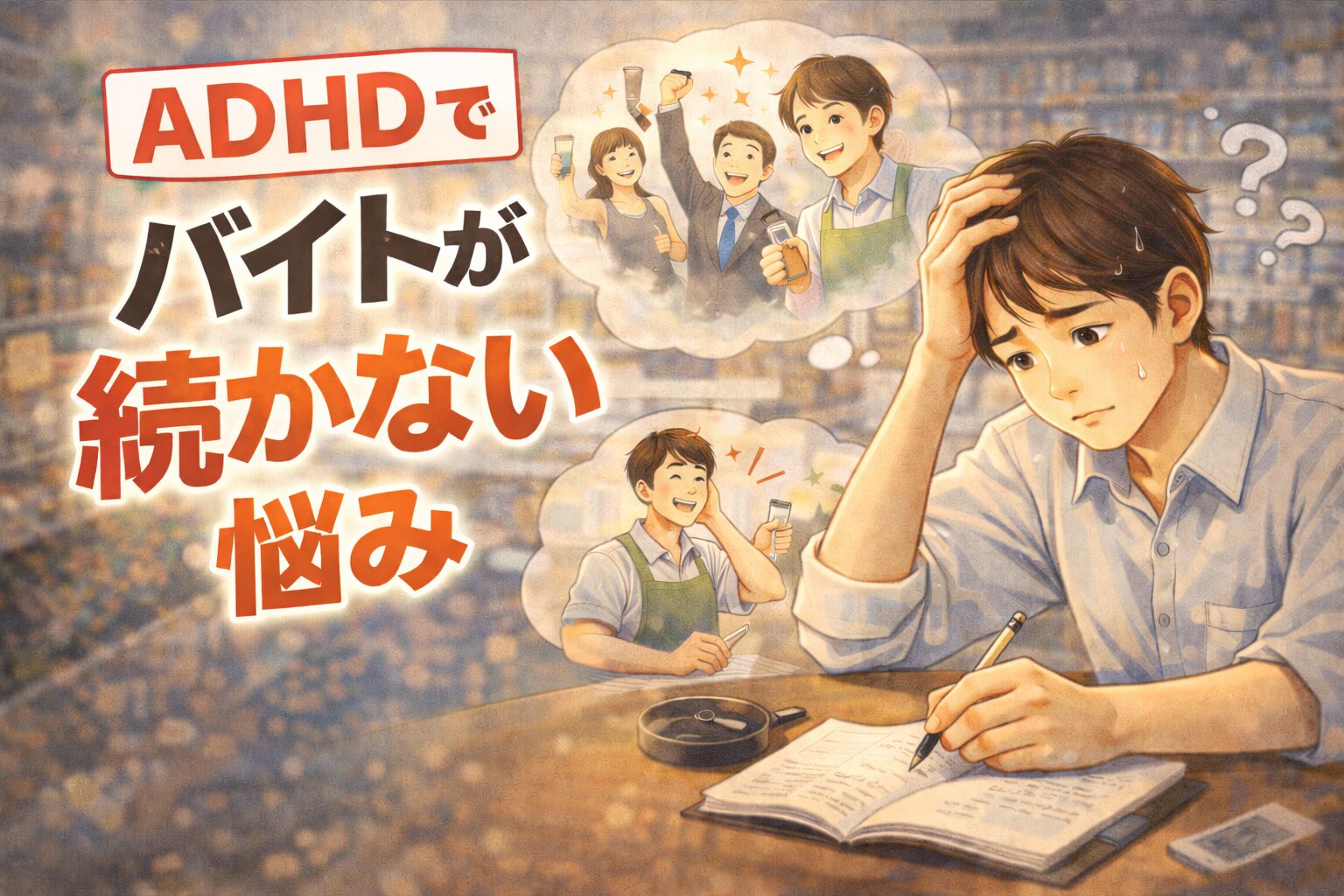ADHDの人がいたら職場はイライラする?原因と対処法を解説

職場の同僚や部下に対して、「なぜ何度も同じミスをするのだろう」「どうしてこんなに落ち着きがないのか」と感じ、日に日に募るイライラに悩んでいませんか。その絶え間ないフラストレーションは、相手の性格や意欲の問題ではなく、ADHD(注意欠如・多動症)という発達障害の特性が背景にあるかもしれません。
この記事では、ADHDの人がいることで職場がなぜイライラする空間になりがちなのか、その原因と特性を深く掘り下げていきます。ADHDの人はイライラしやすいのはなぜか、そしてADHDのイライラが止まらないのはなぜですか、といった脳機能に起因する根本的な疑問から、職場でのADHDの具体的な特徴までを、専門的な知見を交えて詳しく解説します。
Yahoo!知恵袋で見るADHDに関する悩みのように、多くの人が一緒に働くとストレスを感じる理由や、発達障害の人と一緒に働くストレスの実態に直面しているのが現代の職場のリアルです。本記事では、そのストレスを軽減するための具体的な対処法を、あなたの立場に合わせて提案します。
例えば、ADHDの部下との関係に疲れたと感じたらどうすれば良いか、ADHDの同僚にやめてほしいと思う行動への上手な伝え方、職場で迷惑だと思われる典型的なケース、そしてなぜ職場で嫌われることがあるのか、その心理的な背景までを考察。さらには、知らず知らずのうちにあなた自身が陥っているかもしれない「職場カサンドラ症候群」の危険性にも警鐘を鳴らし、最終的にADHDで職場がイライラするときの建設的な接し方について、明日から実践できる解決策を提示します。
- ADHDの特性と職場でイライラが生まれる根本的なメカニズム
- ADHDの人がいる職場で周囲が感じるストレスの正体とその構造
- 上司・同僚・部下という立場別の具体的な関わり方やマネジメント手法
- 自分自身の心を守り、共倒れを防ぐための「職場カサンドラ症候群」に関する知識
ADHDの人がいたら職場はイライラする原因と特性

- ADHDの人はイライラしやすいのはなぜ?
- ADHDのイライラが止まらないのはなぜですか?
- 職場でのADHDの具体的な特徴は?
- 知恵袋で見るADHDに関する悩み
- 一緒に働くとストレスを感じる理由
- 発達障害の人と一緒に働くストレスの実態
ADHDの人はイライラしやすいのはなぜ?
ADHDの人が職場でイライラしやすい根本的な理由は、本人の性格や努力不足ではなく、その脳の機能的な特性である「衝動性」「不注意」「多動性」が、現代社会の職場で求められる遂行能力としばしば衝突するからです。物事が計画通りに進まなかったり、期待されるパフォーマンスを発揮できなかったりする状況が、定型発達の人よりもはるかに頻繁に発生します。
例えば、「衝動性」という特性は、脳の前頭前野の機能が関係しており、行動や感情のコントロールを難しくさせます。これにより、会議で相手の話を最後まで聞かずに発言してしまったり、熟考せずに結論を出してしまったりします。その結果、人間関係の摩擦を生むだけでなく、本人も後から「なぜあんな短絡的なことを…」と激しい自己嫌悪に陥り、ストレスを内面に溜め込んでしまうのです。
また、「不注意」の特性は、単純なケアレスミスや重要な約束の失念を引き起こします。これが一度や二度なら誰にでもあることですが、ADHDの場合は頻度が高く、何度も同じ失敗を繰り返す傾向があります。周囲から「またか」と厳しい叱責や呆れた視線を向けられる経験が積み重なると、「自分は何をやってもダメだ」という無力感に苛まれます。こうした外部からの絶え間ない否定的評価と、それによって蝕まれる自己肯定感の低さが、精神的な余裕を奪い、些細なことでもカッとなりやすい、いわば防衛的なイライラ状態を作り出してしまうのです。
ポイント
ADHDの人のイライラは、本人のわがままや性格の問題と捉えるべきではありません。それは、自分の意志ではコントロールしがたい脳の特性と、周囲の環境とのミスマッチによって生じる、苦痛のサインであると理解することが、問題解決の第一歩となります。
ADHDのイライラが止まらないのはなぜですか?
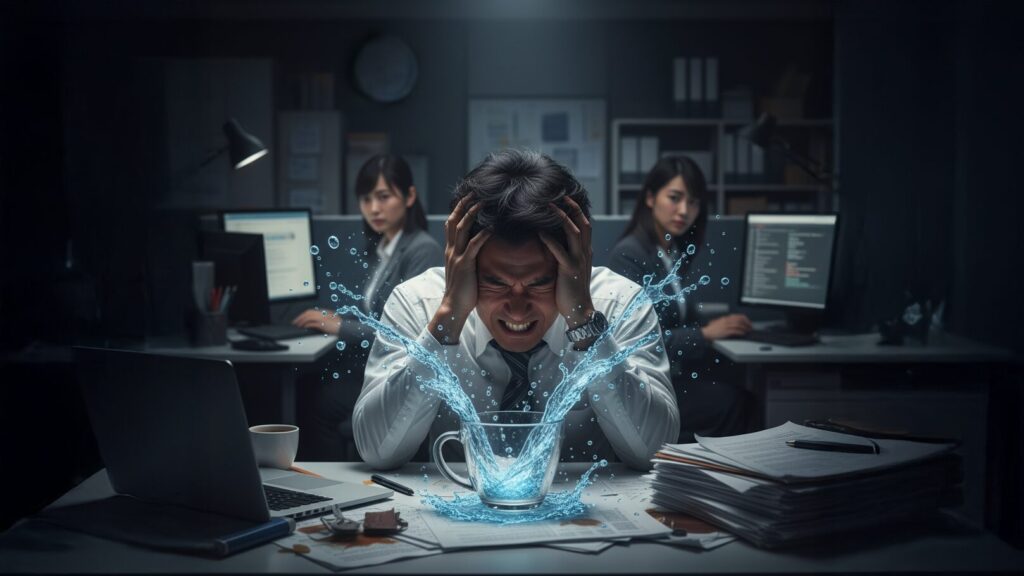
ADHDの人のイライラが一度始まると、なかなか鎮まらなかったり、爆発的な怒りに発展したりする背景には、感情の調節機能の弱さと、慢性的なストレスの蓄積という根深い問題が存在します。ADHDの脳機能特性の一つに「実行機能障害」があり、これは物事を計画・遂行する能力だけでなく、感情のブレーキをかけたり、気持ちを切り替えたりするセルフコントロール能力にも影響を及ぼします。
このため、一度強い怒りや不満を感じると、その感情に思考が支配されてしまい、冷静に状況を分析したり、別の視点から物事を考えたりすることが極端に難しくなります。これは「易怒性(いどせい)」と呼ばれ、特に予期せぬトラブル、急な計画変更、あるいは理不尽だと感じる批判に直面した際に、感情のダムが決壊するように現れることがあります。
さらに、ADHDの人は日常生活のあらゆる場面で、定型発達の人が意識しないレベルの小さなストレスを常に経験しています。
- 「電車の乗り換えを間違えた」
- 「重要なメールの返信を忘れていた」
- 「会話の途中で何を話していたか分からなくなった」
このような失敗体験が毎日降り積もることで、心のキャパシティは常に限界に近い状態にあります。まるで縁まで水が張られたコップのように、ほんの一滴のストレスという水が加わっただけで、感情の水が一気に溢れ出してしまうのです。そのため、周囲から見れば「なぜ、たったそれだけのことで?」と感じるような些細な出来事が、本人にとっては最後の一押しとなり、抑えきれないほどのイライラとして噴出することがあります。
職場でのADHDの具体的な特徴は?

職場環境において顕在化するADHDの具体的な特徴は、主に「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの核心的な領域に分類されます。これらの行動は、本人の能力や職業倫理観とは全く別の次元で、脳の特性として無意識的に現れるため、周囲からは「やる気がない」「社会人としての自覚が足りない」といった深刻な誤解を招きやすいのが実情です。
厚生労働省も発達障害の特性について情報を提供しており、正しい理解が求められています。(出典:こころの情報サイト「発達障害」)
以下に、それぞれの特性が職場でどのような行動として現れるか、具体例を挙げます。
| 特性 | 職場での具体的な行動例 |
|---|---|
| 不注意 (Inattention) | ・メールの宛先(To/Cc/Bcc)や添付ファイルを頻繁に間違える。 ・契約書や見積書などの重要書類で、桁や日付といった致命的なミスを犯す。 ・長時間の会議や研修では集中力が切れ、内容が頭に入らず上の空になる。 ・指示された内容を部分的にしか覚えておらず、自己流の解釈で進めてしまう。 ・デスクの上やPCのデスクトップが常に散乱しており、必要な情報を探すのに時間がかかる。 ・時間を見積もるのが苦手で、常に締め切りに追われるか、遅延してしまう。 |
| 多動性 (Hyperactivity) | ・会議中やデスクワーク中に、貧乏ゆすりをしたり、指で机を叩いたりして落ち着きがない。 ・特に目的もなくオフィス内を歩き回ることがある。 ・頭の中が常に多動な状態(思考が次々に飛ぶ)で、一つの作業に集中できない。 ・早口で一方的に話し続け、相手が口を挟む隙を与えない。 |
| 衝動性 (Impulsivity) | ・相手が話している最中に、結論を先読みして割り込んだり、自分の意見を被せたりする。 ・リスクを十分に検討せず、思いつきで新しいプロジェクトや提案をして周囲を混乱させる。 ・ちょっとしたことでカッとなり、同僚や上司に対して感情的な言葉をぶつけてしまう。 ・順番を待つことが苦手で、コピー機の使用や質問の順番を守れないことがある。 |
補足
これらの特徴は、誰しもが時折見せる行動かもしれません。しかしADHDの場合、これらの行動が年齢や発達水準に不相応なほど顕著に、かつ頻繁に現れ、仕事や人間関係といった社会的な機能に深刻な支障をきたしているという点で、決定的に異なります。
知恵袋で見るADHDに関する悩み
Yahoo!知恵袋のような匿名のQ&Aサイトは、ADHDを持つ人々と働く上での生々しい悩みが集まる場所であり、現代の職場が抱える課題を映し出す鏡と言えます。投稿される相談内容は、職場におけるADHDへの理解と適切なサポート体制がいかに不足しているかを痛感させます。
典型的な悩みは、主に部下、同僚、上司という3つの関係性で見られます。
- 部下への悩み:「ADHDグレーゾーンの部下が、何度同じミスをしても『すみません』と言うだけで改善しません。マニュアルを渡しても読まず、口頭で説明しても忘れます。指導するこちらの精神がもう限界です。どうすれば彼の心に響くのでしょうか?」
- 同僚への悩み:「空気が読めず、悪気なく失言を繰り返すADHDの同僚がいます。取引先との重要な商談でも、相手の機嫌を損ねるような発言をしてしまい、いつも私が後処理に追われます。彼のフォローに疲れ果てました。」
- 上司への悩み:「ADHD気質の上司は、指示が毎回コロコロ変わります。昨日言っていたことと今日言っていることが真逆で、報告したことも完全に忘れられている。一体何を信じて仕事を進めれば良いのか分からず、チーム全体が疲弊しています。」
これらの悲痛な叫びから浮かび上がるのは、周囲の人々がADHDの人の行動を「本人の性格、能力、あるいは意欲の問題」として個人的なレベルで解釈し、その結果、どう対処すれば良いか分からずに行き詰まり、疲弊しきっているという共通の構図です。特性への正しい理解がなければ、有効な対策を講じることはできず、ただ感情的な対立や根性論に陥り、ストレスだけが蓄積されていくのです。
多くの人が「自分がもっと我慢すれば丸く収まるのか」「どうすれば相手は『普通』になってくれるのか」という、出口のない問いに苦しんでいます。しかし、本当に必要なのは相手を変えようとすることではありません。相手の特性を前提とした上で、関わり方や業務の進め方、環境そのものを調整するという、より建設的な視点を持つことが求められています。
一緒に働くとストレスを感じる理由
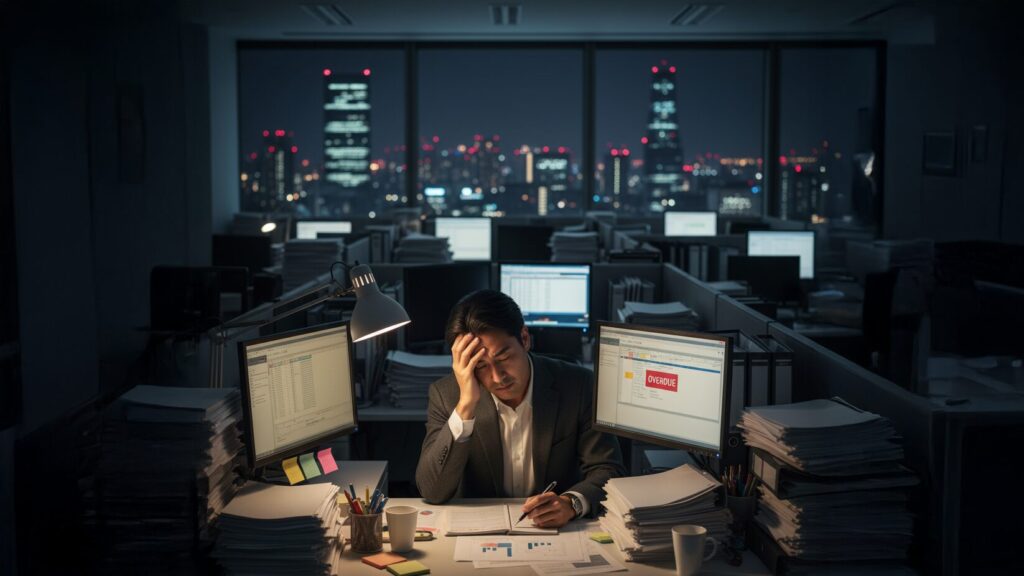
ADHDの人と共に働くことで周囲が強いストレスを感じる最大の理由は、その行動の予測不能性と、それによって引き起こされるコミュニケーションの齟齬が、周囲の従業員に過剰な精神的・物理的負担を強いるという点にあります。
まず、ADHDの「不注意」特性から生じるケアレスミスやタスクの抜け漏れは、目に見える形で同僚や上司の業務量を増加させます。例えば、顧客リストの入力を一つ間違えるだけで、営業部門全体に誤った情報が共有されてしまうかもしれません。たった一つの締め切りを守れないことで、プロジェクト全体のスケジュールが破綻し、チーム全員が深夜までの残業を強いられることもあり得ます。
こうした度重なる「尻拭い」や「リカバリー作業」は、「なぜ自分ばかりが彼のミスのために時間と労力を割かなければならないのか」という強い不公平感を生み、職場全体の士気を著しく低下させる要因となります。
また、「衝動性」からくる言動も、目には見えない深刻なストレスを与えます。会議の論点を無視した突然のアイデア披露や、相手の立場を考慮しないあまりにも正直すぎる意見は、職場の調和を乱し、人間関係に亀裂を生じさせます。たとえ相手に悪気がないことが分かっていても、その発言によって傷ついたり、困惑したりする感情的な負担は避けられません。
注意点
このような状況が常態化すると、周囲の従業員は常に気を張り詰め、「次に彼は何をしでかすのだろうか」という慢性的な警戒状態に置かれることになります。この絶え間ない精神的な緊張と疲労こそが、ADHDの人と一緒に働く上で最も蝕まれる、根深いストレス源と言えるでしょう。
発達障害の人と一緒に働くストレスの実態

職場で生じるストレスは、ADHD単独の特性だけでなく、ASD(自閉スペクトラム症)など他の発達障害の特性が複雑に絡み合うことで、さらに根深く、対処が困難な問題となることがあります。
ADHDとASDは併存するケースも少なくなく、その場合、それぞれの特性が互いに影響を及ぼし合い、周囲の混乱やストレスを指数関数的に増大させることがあります。一見すると矛盾した行動に見えるため、周囲は対応に苦慮します。例えば、以下のようなケースが考えられます。
ケース1:ADHDの「不注意」とASDの「強いこだわり」の併存
普段はケアレスミスが多く、書類の提出期限を忘れがち(ADHDの特性)である一方、一度自分が決めた作業手順やファイルの命名規則といったマイルールには、異常なまでに執着する(ASDの特性)人がいます。業務効率化のために新しいツールやフローを提案しても、「今までのやり方でないと混乱する」と頑なに拒否するため、チーム全体の生産性向上が阻害されるというストレスが生じます。
ケース2:ADHDの「衝動性」とASDの「社会的想像力の困難」の併存
思ったことをフィルターを通さずにすぐ口にしてしまう(ADHDの特性)上に、相手の表情や声のトーン、場の雰囲気といった非言語的な情報から相手の感情を推察することが苦手(ASDの特性)なため、本人に全く悪気がないまま、相手のコンプレックスを刺激するような発言や、TPOをわきまえない質問をしてしまうことがあります。冗談や皮肉が通じず、言葉の額面通りに受け取って真顔で反論されると、円滑なコミュニケーションを諦めざるを得ない状況に陥ります。
このように、複数の発達障害の特性が複雑に混在している場合、その人の行動パターンは一貫性がなく、矛盾しているように見えるため、周囲は「彼の『地雷』がどこにあるのか分からない」「一体どういう基準で動いているんだ」と、常に戸惑いと不安を感じ続けることになります。この「理解不能性」こそが、コミュニケーションにおける最も深刻なストレスの実態と言えるのです。
ADHDの人がいて職場でイライラするときの対処法
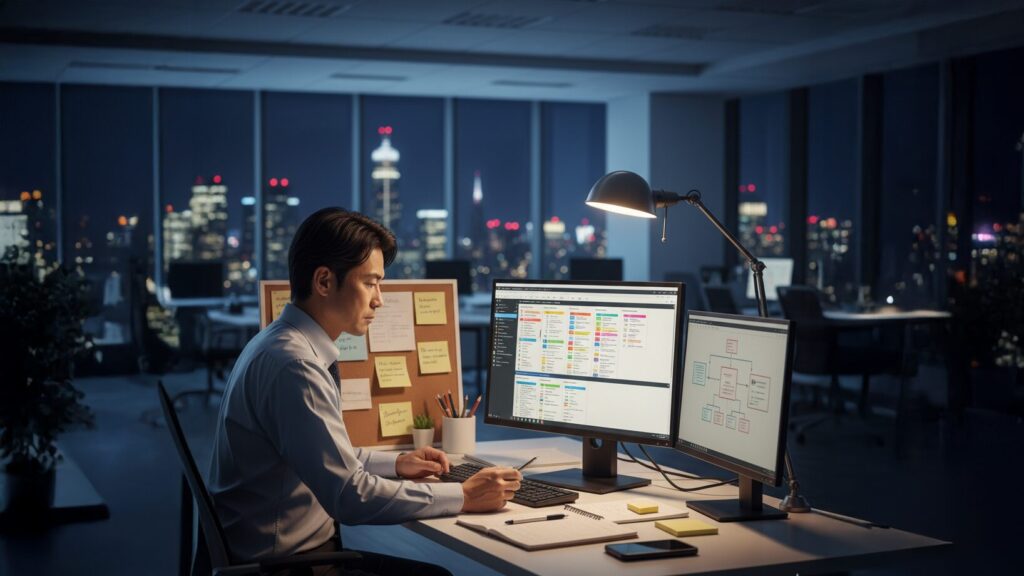
- ADHDの部下との関係に疲れたと感じたら
- ADHDの同僚にやめてほしいと思う行動
- 職場で迷惑だと思われるケースとは
- なぜ職場で嫌われることがあるのか
- あなたも?職場カサンドラ症候群とは?
- ADHDで職場がイライラするときの接し方
ADHDの部下との関係に疲れたと感じたら
ADHDの特性を持つ部下への指導に心身ともに疲れを感じたとき、最も重要なのは「一人で完璧なマネジメントをしよう」という考えを手放すことです。管理職としての強い責任感から「部下の問題は全て自分の責任だ」「自分が何とか成長させなければ」と思い詰めてしまうと、過剰なストレスを抱え込み、最終的には共倒れという最悪の事態を招きかねません。
まずは、感情的に叱責したり、根性論で奮起を促したりするアプローチから脱却しましょう。そして、部下の特性を前提とした上で、具体的な「仕組み」や「環境」でサポートするという、より建設的なマネジメント手法に切り替えることが極めて重要です。
【具体的なアプローチ】
- 指示の出し方を徹底的に工夫する(視覚化・具体化・単純化)
口頭での指示は、ADHDの人のワーキングメモリの特性上、抜け落ちやすいと考えましょう。チャット、メール、タスク管理ツール(TrelloやAsanaなど)、あるいは古典的な付箋など、必ず「目で見て確認できる形」で残すことを徹底します。「なるべく早く」「いい感じに」といった曖昧な表現は厳禁です。「〇月〇日の15時までに、このフォーマットを使って、A社向けの提案書を3部作成してください」というように、5W1Hを明確にした具体的な指示を心がけましょう。 - タスクをベビーステップにまで細分化する
「来月末までに新商品のプレゼン資料を作成する」といった大きなタスクは、ADHDの人にとってどこから手をつけていいか分からず、先延ばしの原因になります。これを「①市場調査」「②競合分析」「③コンセプト設計」「④構成案作成」「⑤デザイン作成」のように細かく分解し、それぞれに小さな締め切りを設定します。一つ一つのステップをクリアしていくことで、部下は達成感を得やすくなり、上司も進捗を正確に把握できます。 - 定期的かつ短期的な1on1ミーティングを設定する
週に1回30分、あるいは毎朝5分でも構いません。定期的に1対1で話す時間を確保し、「今、何に一番困っている?」「タスクの優先順位はこれで合っている?」といった具体的な確認を行います。これにより、問題が大きくなる前に早期発見・早期修正が可能となり、認識のズレを防ぎます。 - 「個人」ではなく「チーム」でサポートする体制を築く
あなた一人で全てのフォローを行う必要はありません。「彼の〇〇という特性は、チームのこの業務フローだとミスが起きやすいから、チェック体制を強化しよう」というように、個人の問題ではなく「チームの仕組みの問題」として課題を提示し、メンバー全員でサポートする文化を醸成します。人には相性もあるため、他のメンバーが指導した方がスムーズに進むこともあります。 - 人事部や専門機関といった「外部の力」を積極的に頼る
どうしても改善が難しい場合は、決して一人で抱え込まず、人事部や産業医、あるいは地域の障害者職業センターなどの専門機関に相談してください。これは管理職としての責任放棄ではなく、部下にとってより適切なサポートを見つけ出すための、賢明かつ責任ある判断です。企業には障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」の提供義務があり、専門家のアドバイスを求めることはその一環でもあります。(参考:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」)
ADHDの同僚にやめてほしいと思う行動

ADHDの同僚が見せる特性由来の行動に対して、積もり積もった不満から「いい加減にしてほしい!」と感じたとき、その感情を直接的にぶつけることは、関係を悪化させるだけでほとんどの場合、解決にはつながりません。相手を非難するのではなく、「あなたの〇〇という行動によって、私の業務に△△という支障が出ている(客観的な事実)」と、「だから、□□という形にしてもらえると、私はとても助かる(具体的な要望・代替案)」という2点をセットにして、冷静かつ丁寧に伝えるアプローチが極めて有効です。
このコミュニケーション手法の核となるのが、主語を「あなた(You)」から「私(I)」に転換する「アイメッセージ(I-message)」です。これは、相手を主語にして断定・評価する(Youメッセージ)のではなく、自分を主語にして自分の感情や状況を表現する方法です。
| 場面 | NGな伝え方(Youメッセージ:相手を責める) | OKな伝え方(Iメッセージ:自分の状況と要望を伝える) |
|---|---|---|
| 集中したい時に頻繁に話しかけられる | 「(あなたは)本当に空気が読めない!いつも集中を妨げるように話しかけてきて、迷惑千万だ!」 | 「ごめん、今(私は)このレポートの締め切りが迫っていて、すごく集中したいんだ。だから、15時に終わる予定だから、その後に声をかけてくれると、しっかり話が聞けてすごく助かるんだけど、どうかな?」 |
| 共有スペースがいつも散らかっている | 「(あなたは)共有の棚をいつもぐちゃぐちゃにして、本当にだらしない!社会人としてどうなの?」 | 「(私は)次に使う人が気持ちよく使えるように、使い終わったハサミは元の場所に戻しておいてもらえると、探す手間が省けて嬉しいな。」 |
| 会議で話を遮られる | 「(あなたは)会議でいつも人の話を遮って、自分の話ばかりする!協調性というものがないのか?」 | 「(私は)あなたの意見もぜひ聞きたいんだけど、まずはAさんの話を最後まで聞いてからにしてもらえると、議論の流れが分かりやすくなって助かるんだ。」 |
最も重要なのは、相手の人格や意欲を否定するのではなく、あくまでも「客観的に観察できる行動」そのものに焦点を絞ることです。ADHDの人は悪気なく、また無意識にそれらの行動をとっている場合が多いため、「そうか、自分のこの行動が、具体的にこういう影響を与えていたのか」と気づくきっかけを与えられれば、前向きな行動変容につながる可能性が高まります。
職場で迷惑だと思われるケースとは

ADHDの特性に起因する行動が、職場で単なる「個性的」や「うっかり」の範囲を超え、深刻な「迷惑」だと捉えられてしまうのは、その行動が周囲の従業員の業務遂行に直接的な実害を与えたり、組織全体の信用や安全性を脅かしたりする場合です。本人に悪意がないことは周囲も薄々理解していても、具体的な損害が発生すると、どうしても許容範囲を超え、ネガティブな評価に直結してしまいます。
具体的には、以下のようなケースが典型例として挙げられます。
職場で「迷惑行為」と見なされやすい行動例
- 会社の信頼を根底から揺るがすミス:
顧客へのメールで宛先を全件BccではなくToに入れてしまい個人情報を流出させる、契約書や請求書の金額を桁違いに間違えて重大な金銭的損害を発生させるなど、会社の信用問題に発展しかねない致命的なケアレスミス。 - チームの機能を麻痺させる行動:
業務に必要な「報告・連絡・相談」を怠り、自己判断で勝手に仕事を進めた結果、大きなトラブルを発生させ後処理にチーム全員を巻き込む。重要なタスクの締め切りを破り、プロジェクト全体の遅延と信用の失墜を招く。 - 組織の規律や安全を軽視する問題:
明確な理由なく遅刻や無断欠勤を繰り返し、周囲の勤務意欲を削ぐ。製造現場や医療現場などで、定められた安全確認の手順を省略し、事故のリスクを高める。 - 修復困難な対人関係トラブル:
重要な顧客や取引先に対して、TPOをわきまえない失礼な発言をしてしまい、商談を破談に追い込む。感情のコントロールができず、職場で大声で怒りを爆発させ、他の従業員を萎縮させたり、職場の雰囲気を破壊したりする。
これらの行動は、本人の「うっかりしていた」という弁解では済まされない、深刻な結果を引き起こす可能性があります。もちろん、人間であれば誰でも一度は失敗を犯します。しかし、同様の重大な問題が教育や指導にもかかわらず繰り返し発生し、改善への具体的な努力が見られない場合、周囲の忍耐も限界に達し、「チームにいるだけでリスクになる迷惑な存在」という厳しいレッテルを貼られてしまうことになりかねません。
なぜ職場で嫌われることがあるのか
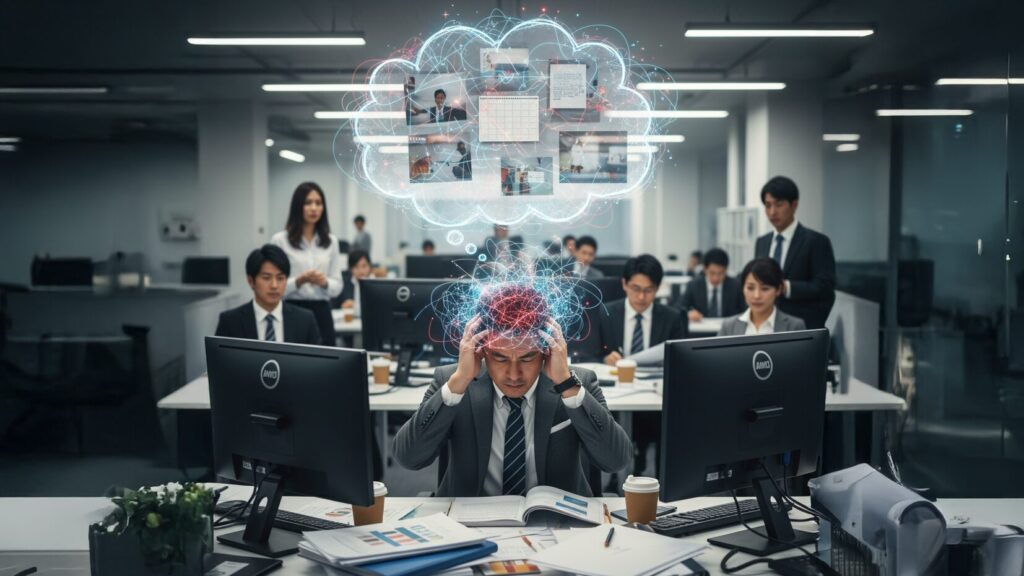
ADHDの人が職場で人間関係に悩み、「嫌われている」と感じてしまうことがあるとすれば、その根本的な原因は、その人の行動の背景にある脳の特性が周囲に全く理解されず、悪意、怠慢、あるいは性格の欠陥といったネガティブな意図の表れとして誤解されてしまうという、悲しいコミュニケーションの断絶に尽きます。
ほとんどの人は、無意識のうちに自分自身の「常識」や「当たり前」という価値観のフィルターを通して他人を評価します。そのため、「社会人としてこのくらいできて当然」とされる事柄(時間や納期を守る、ミスなく作業を遂行する、場の空気を読んで円滑なコミュニケーションをとるなど)が、本人の努力ではどうにもならないレベルで困難なADHDの人に対して、次のような厳しい解釈を下してしまいがちです。
| ADHDの特性による行動 | 周囲によるネガティブな誤解 |
|---|---|
| ケアレスミスを繰り返す | → 「仕事に対するやる気がない」「真剣さや責任感が欠けている」「反省していない証拠だ」 |
| 約束や指示を忘れる | → 「相手を軽視している」「人を馬鹿にしている」「不誠実で信用できない人物だ」 |
| 場の空気が読めない言動 | → 「自己中心的で思いやりがない」「わざと人を不快にさせている」「協調性を乱すトラブルメーカーだ」 |
このような誤解に基づく一方的なラベリングが積み重なると、本人に対する根強い不信感や、時には嫌悪感へと発展してしまいます。一方で、ADHDの本人は、自分なりに必死に努力し、周囲に迷惑をかけないようにと常に気を張っているにもかかわらず、なぜかうまくいかず、誰からも理解されないという深い孤独感と疎外感を抱えています。この埋めがたい認識の溝が、両者の関係を修復不可能なレベルまで悪化させる、負のスパイラルを生み出してしまうのです。
つまり、「嫌われる」という現象は、ADHDの特性そのものが直接的な原因なのではなく、その特性と、それに対する周囲の無理解や知識不足が激しく衝突することによって引き起こされる、コミュニケーションの悲劇であると言えるのです。
あなたも?職場カサンドラ症候群とは?

「特定の同僚や部下の言動に毎日振り回され、理由の分からないイライラと疲労感で心身ともに限界だ…」もしあなたがこのような状態にあるなら、それは単なる「仕事のストレス」ではなく、「職場カ常にサンドラ症候群」に陥っている危険信号かもしれません。
カサンドラ症候群は、正式な医学的診断名ではありませんが、発達障害(特にASDの特性である共感性や社会的想像力の困難)を持つパートナーや家族、同僚などとの間で、情緒的な意思疎通が著しく困難なために、支援する側が深刻な心身の不調をきたしてしまう状態を指す言葉です。ギリシャ神話の、真実を予言しても誰にも信じてもらえない王女カサンドラの悲劇に由来します。
職場でこの症候群に陥ると、以下のような特徴的な症状が現れます。
職場カサンドラ症候群の主な症状・特徴
- 相手の言動の意図が全く理解できず、常に混乱し、強いイライラや無力感に苛まれる。
- 論理的な会話や感情的な共感が得られないため、職場にいるのに強い孤独感や疎外感を感じる。
- この辛さを上司や他の同僚に相談しても、「考えすぎだよ」「彼に悪気はないんだから」「あなたにも何か原因があるんじゃない?」などと理解してもらえず、二次的に傷つき、さらに孤立を深める。
- 次第に「自分のコミュニケーション能力が低いからだ」「自分の心が狭いのが悪いんだ」と自己肯定感が著しく低下し、自分を責め始める。
- 精神的な症状:
抑うつ気分、強い不安感、仕事への意欲の完全な喪失、集中力や判断力の低下など。 - 身体的な症状:
原因不明の頭痛やめまい、不眠や過眠、動悸や息苦しさ、胃痛や過敏性腸症候群、慢性的な疲労感など、自律神経系の失調が顕著に現れる。
ADHDの人との関係においても、衝動的な言動に振り回されたり、話が噛み合わなかったりする状況が長期化すると、カサンドラ症候群に類似した深刻な状態に陥ることがあります。最も重要なのは、「今の自分の心身の不調は、自分の弱さのせいではなく、健全なコミュニケーションが成立しないという『関係性』の問題から生じているのかもしれない」と客観的に認識することです。一人で抱え込まず、社内の相談窓口やカウンセラー、心療内科といった専門家の助けを求め、まずは自分自身の心と体を守ることを最優先に行動してください。
ADHDの人が職場にいてイライラするときの接し方

ADHDの人がいることで職場全体にイライラが蔓延し、生産性が低下している状況を根本的に改善するためには、相手の「特性」という変えられない部分を無理に変えさせようとするアプローチをきっぱりと諦めることが出発点となります。本人の意志や努力だけでは限界がある脳の機能特性の問題を、周囲が「関わり方」と「環境」の工夫によって、いわば外部からサポートしていくという発想の転換が不可欠です。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)なども、発達障害のある方々が働きやすい職場環境整備の重要性を説いています。(出典:JEED「障害者雇用マニュアル 発達障害者と働く」)
以下に、明日からでもすぐに実践できる、具体的な接し方のポイントを挙げます。
- 指示は「具体的」「視覚的」「肯定的」に
「あれ、適当によろしく」のような曖昧な指示は、混乱とミスの元凶です。「この資料(現物を見せる)を、A4サイズで3部カラーコピーして、10時までにA会議室のテーブルの上に置いてください」というように、5W1Hを明確に、具体的な行動レベルで伝えます。さらに、口頭での指示と合わせて、チャットやメールでテキストとして残す「視覚的」なサポートが極めて有効です。「〇〇しないように」という否定形の指示よりも、「〇〇してください」という肯定形の指示の方が、行動に移しやすくなります。 - 一度に指示する情報は「一つだけ」に絞る
ADHDの人は、複数の情報を同時に記憶し、処理するワーキングメモリが弱い傾向にあります。「Aをして、次にBをして、それからCをお願い」と一度に伝えると、Aしか覚えていない、あるいは全てが混ざってパニックになることがあります。手間のように感じても、指示は一つずつ出し、それが完了したことを確認してから次の指示を出すという「シングルタスク」の原則を徹底しましょう。 - 「弱み」の克服より「強み」を活かす配置転換
細かい事務作業やルーティンワークでミスを繰り返す人に、根性論でそれを克服させようとするのは非効率的です。むしろ、その人が持つユニークな強みに目を向け、それを活かせる業務に配置する方が、本人にとっても組織にとってもはるかに有益です。例えば、創造性や発想力が豊かであれば企画・開発部門、高い集中力(過集中)を発揮できるなら専門的なリサーチ業務、エネルギッシュで行動力があるなら営業やイベント運営など、適材適所を真剣に検討します。 - ポジティブなフィードバックを意識的に増やす
ADHDの人は、幼少期から叱責される経験が多いため、自己肯定感が低い傾向にあります。ミスを指摘することも必要ですが、それ以上にできたこと、改善した点、努力しているプロセスを具体的に見つけて褒めることが、本人のモチベーションと成長を促す上で絶大な効果を発揮します。「先週お願いした件、忘れずにやってくれて助かったよ、ありがとう」といった小さな承認の言葉が、信頼関係を築く土台となります。 - 問題発生時は「感情」ではなく「仕組み」で解決する
ミスが起きた際に、「なぜ、また同じ失敗をするんだ!」と感情的に叱責しても、相手を萎縮させるだけで再発防止にはつながりません。「このミスが起きたのは、チェックリストがなかったからかもしれないね。次回からこのリストを使って確認する仕組みにしよう」というように、個人を責めるのではなく、ミスが起きにくい「仕組み」や「ルール」を一緒に考えるという姿勢で臨みましょう。
まとめ:ADHDで職場がイライラするときの接し方
- ADHDによるイライラの原因は本人の性格ではなく脳の特性にあると理解する
- 衝動性や不注意からくるミスや感情の起伏がイライラの引き金になりやすい
- 周囲は予測不能な行動やコミュニケーションの齟齬にストレスを感じる
- ミスや遅延のフォローが常態化すると不公平感が募る
- 一人で抱え込まず上司や人事部、チーム全体で対応策を考える
- 指示は曖昧さをなくし具体的かつ視覚的に伝えるのが基本
- 一度に多くのタスクを振らず一つずつ着実に進めてもらう
- タスクは細かく分解し優先順位を明確に示す
- 定期的な進捗確認で認識のズレを早期に修正する
- 苦手なことの克服より得意なことを活かせる役割を考える
- できたことは具体的に褒めて自己肯定感を育む
- 問題が起きても感情的にならず事実と対策を冷静に伝える
- 話が通じないストレスが続く場合は職場カサンドラ症候群を疑う
- 自分自身のメンタルヘルスを守ることを最優先に行動する
- 相手を変えようとするのではなく環境や仕組みでサポートする視点を持つ
人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)
発達障害ランキング