ADHD向いてる仕事、2chの本音と適職
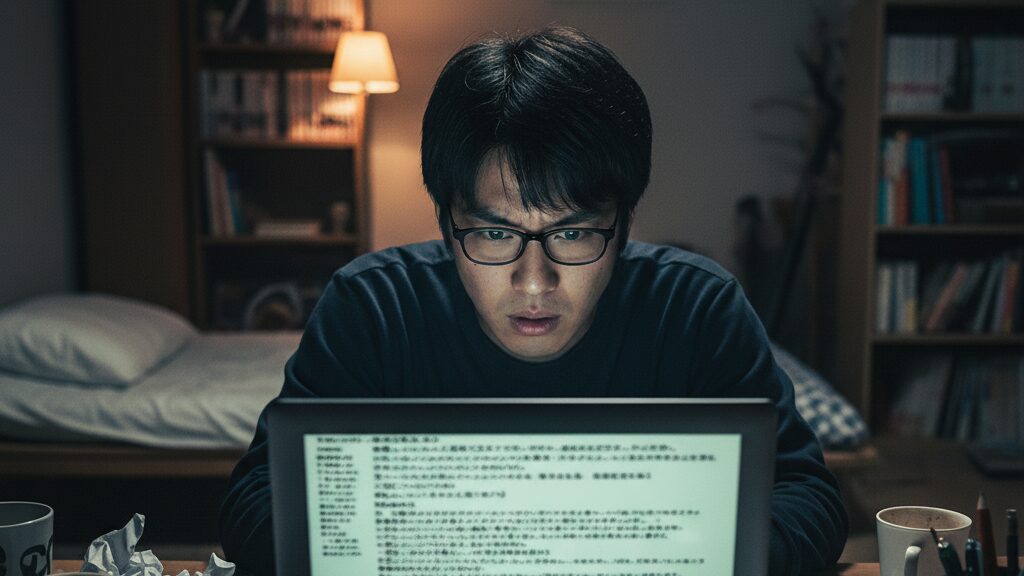
こんにちは。発達グレーとライフデザイン手帖、運営者の「ひかり先生」です。
「adhdの向いてる仕事」について2ch(現5ch)などで情報を探している時って、本当に切実な悩みがある時かなと思います。
医療機関や支援機関がすすめる「公式の適職リスト」、例えば「デザイナー」や「エンジニア」といったキラキラした職業は、なんだか現実味がなくて…。それよりも、もっとリアルな「本音」が知りたい。そう思うのは、とても自然なことですよね。
特に、事務職がどうしても続かないとか、adhdの女性特有の働きにくさを感じていたり、あるいは自分はグレーゾーンかもしれないと悩んでいたりすると、周りに相談しにくいこともあるかもしれません。
この記事では、そうした匿名の掲示板で語られる「本音」の部分を深掘りしながら、adhdの特性と仕事の「ミスマッチ」について、その構造的な理由と、じゃあどうすればいいのか、という対策を一緒に考えていきたいと思います。
- 2chで語られる「事務職が続かない」本当の理由
- ADHDの特性が活きる「意外な適職」の分析
- 女性やグレーゾーンの人が抱えやすい仕事の悩み
- 「仕事が続かない」悩みへの具体的な対策
ADHDの向いてる仕事、2chの本音

「公式」の適職リストは、ADHDの「強み」である発想力や行動力にフォーカスしがちです。でも、2chなどの掲示板で語られるのは、むしろ「弱み」がどう仕事に影響したか、という生々しい「失敗談」や、そこから見えてきた「意外な成功体験」です。
まずは、なぜ多くの当事者が「簡単」とされる仕事で「詰んでしまう」のか、その構造から見ていきましょう。
ADHDは事務職でなぜ詰むのか
ADHD当事者の方が社会に出て、最初にぶつかる大きな壁が「一般事務」や「経理」などのオフィスワークかもしれません。掲示板でも、事務職での失敗談は本当に多く語られています。
なぜ事務職が「地獄」になり得るかというと、その理由は「事務職のマルチタスクの多さ」と「ADHDのマルチタスクの苦手さ」が致命的にミスマッチだから、というのが私の見解です。
ADHDの特性として、物事の優先順位をつけることや、計画を立てて実行することが苦手な場合があります(実行機能の課題と言われます)。一つの作業(シングルタスク)だけなら問題なくても、実際の事務職は違いますよね。
例えば、こんな経験はありませんか?
ワーキングメモリの崩壊例
- 集中して書類作成(タスクA)をしている。
- 途中で電話(タスクB)が鳴り、対応する。
- 電話を切った直後、上司から「急ぎでこれコピーしといて」(タスクC)と割り込まれる。
- コピー(タスクC)を終えて席に戻った時、最初にやっていたタスクAのことをすっかり忘れてしまう…。
これは「やる気がない」とか「真面目にやっていない」のではなく、脳のワーキングメモリ(作業記憶)が、次々と入る「割り込み」によって完全にオーバーフローしている状態なんです。
「苦手」が凝縮された業務内容
事務職は、まさにこの「割り込みが常態化した業務環境」なんですね。それだけでなく、ADHDの特性と衝突しやすい業務が凝縮されています。
- ケアレスミスが許されない: 経理の数字入力、契約書の宛名など、小さなミスが大きな問題に直結します。「不注意」特性と相性が悪く、常に緊張を強いられます。
- 優先順位付けの連続: 「電話対応」「来客対応」「上司の指示」「定例業務」…どれから手をつけるべきか瞬時に判断し続ける必要があり、実行機能に大きな負荷がかかります。
- 段取りと計画性: 「月末までにこの作業を終える」ために、逆算してスケジュールを立て、淡々と進めることが求められますが、これがとても苦手な場合があります。
書類を揃える、順序だてて淡々と進める、といった業務の本質が、ADHDの特性(不注意、多動性、衝動性)と衝突しやすい構造になっている、と私は考えています。
ADHDの営業職と付随する事務

「じゃあ、事務がダメなら営業職ならどう?」という声も聞きます。確かに、ADHDの「フットワークの軽さ」や「行動力」「好奇心旺盛さ」が、新規開拓や商談で活きる、というのはよく言われることです。
しかし、ここにも大きな「罠」があると私は思っています。
それは、どんなに「営業(訪問や商談)」自体が適職だったとしても、その前後に「ADHDが最も苦手とする事務作業」が大量に発生するという現実です。
営業職に付随する「事務」の例
- 訪問前のアポイント調整、スケジュール管理
- 顧客情報のデータベース入力、整理
- 提案資料の作成(細かい体裁の調整など)
- 訪問後の報告書(日報)の作成
- 交通費や接待費の経費精算
「商談は得意だし契約も取れるけど、報告書作成を先延ばしにしていつも怒られる」「経費精算が面倒すぎて、結局数ヶ月分溜めてしまい自腹を切ってしまう」…こんな本音が2chで語られるのも、この「適職(営業)」と「不適な事務」がセットになっているからなんですね。
結果として、営業成績は良くても、こうした「事務処理能力」の低さを理由に評価が上がらず、辛くなってしまうケースも少なくないようです。
ADHDの仕事が続かない理由
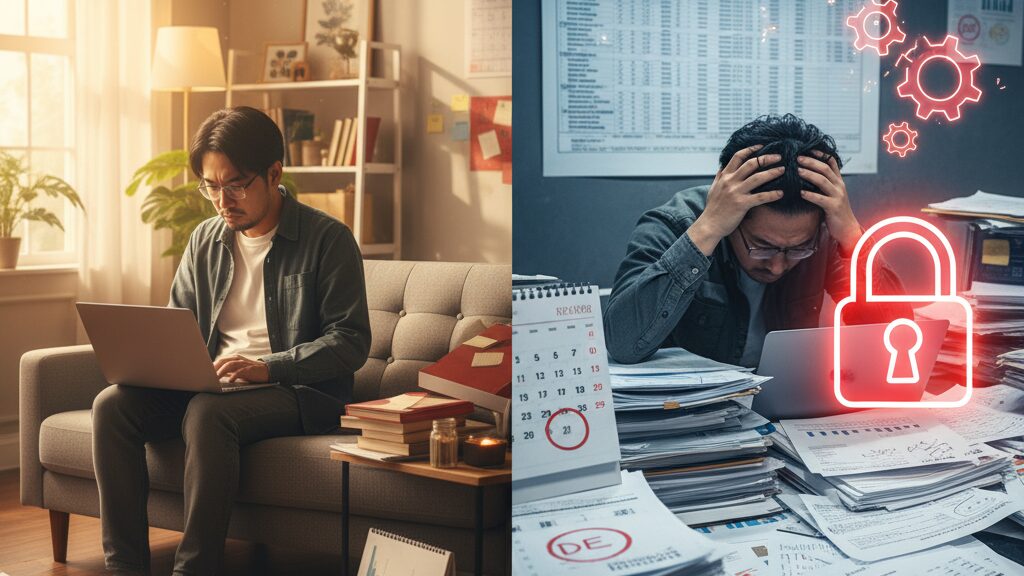
「どの仕事も続かない」と悩んでしまう背景には、こうした「脳の特性」と「職場の環境・業務内容」のミスマッチが根本にあることが多いかなと思います。
特に、ADHDの「衝動性」と「見積もりの甘さ」が組み合わさると、職場で「破滅のサイクル」が生まれやすいです。
「安請け合い」から始まる負の連鎖
「役に立ちたい」「期待に応えたい」という気持ちや、その場の空気から、自分のキャパシティを正確に見積もる前に「はい、やります!」「大丈夫です!」と安請け合いしてしまう…。
でも、いざ持ち帰ってみると「あれ、これどう考えても無理かも…」と気づく。しかし、すでに「できる」と言ってしまった手前、相談もできず…。
結果、タスク管理が追いつかず、優先順位もつけられず、パニックになって先延ばしにしてしまう。最終的に、締め切りギリギリで低品質なものを提出するか、間に合わずに「できませんでした」となってしまう。
これが繰り返されると、「あいつは嘘をつく」「無責任だ」という不本意な評価につながり、自己肯定感が下がり、人間関係も悪化して…最終的に「もう辞めたい」「自分は社会不適合者だ」となってしまう。これは本当に辛いサイクルです。
ADHDの仕事が続かない時の対策
「じゃあ、もう転職するしかないの?」と思いますよね。でも、その前に、今の職場でできる「ライフハック」もたくさん議論されています。
大切なのは「気合で頑張る」ことではありません。ADHDの特性として弱い「実行機能」や「ワーキングメモリ」を「外部のシステムに肩代わりさせる」という考え方です。
タスクの「分解」と「見える化」
ADHD当事者の方は、タスクが「ざっくり」していると、何から手をつけていいか分からず混乱して手が止まりがち、という傾向があるかもしれません。私が見てきた中でも、これが一番効果的かなと思う方法です。
例えば「レポートを出す」という曖昧なタスクを、「行動レベル」まで徹底的に分解します。
「レポートを出す」の分解例
- 何を書くか、キーワードだけメモする(5分)
- Wordで下書きを(誤字脱字気にせず)バーッと書く(30分)
- 一度休憩する(5分)
- 下書きを読み直し、修正する(15分)
- 上司にチャットで下書きを確認してもらう
- OKならPDFに変換する
- メールに添付して送る
ここまで分解すると、「今、何をすべきか」が明確になり、「できそうな感じ」がしてきませんか?この「次の一歩が明確になる」ことで、行動へのハードル(実行機能の負荷)が劇的に下がるんです。これをチェックリストにして、終わったら線を引いて消していきます。
「外部脳」を徹底活用する
ワーキングメモリの弱さは、「頭の外にある記憶装置(外部脳)」で補います。
- スマホのリマインダー: 「〇時に〇〇さんに電話する」など、忘れてはいけないタスクは即座に登録します。
- Googleカレンダー: 予定はすべてここに入れます。移動時間もブロックしておくと、ダブルブッキングを防げます。
- タスク管理アプリ: TodoistやTime Treeなど、自分に合うものを見つけて、やるべきことをすべて書き出します。
- 持ち物の「前日準備」: 朝はワーキングメモリの負荷が最も高い時間帯です。持ち物や着ていく服は、前日の夜にすべて準備しておくことで、忘れ物を劇的に減らせます。
ADHDに向く仕事、清掃業の分析

「公式」のリストには載らない一方で、2chや海外の掲示板(Reddit)で「意外と向いてる」と話題になるのが「清掃業(掃除)」です。
「え、でもADHDって部屋の片付け苦手じゃん?」と思いますよね。この矛盾が、適職を考える上で一番おもしいポイントだと私は思います。
「家庭での掃除(苦手)」と「仕事としての清掃(適職)」は、似て非なるものです。
| 家庭の掃除(苦手) | 「いつ」「どこを」「どの手順で」「どこまでやるか」が全て曖昧。ADHDが最も苦手な「計画・優先順位付け・実行」の塊です。「どこから手をつけていいか分からない」とフリーズしがちです。 |
|---|---|
| 仕事の清掃(適職) | ホテルの客室清掃やビルの定期清掃は、「この部屋を」「このマニュアルの手順で」「この時間までに」と、タスクが完全に具体化・マニュアル化されています。 |
なぜ「仕事の清掃」は向いているのか?
つまり「清掃業」は、第1部で見た「事務職」の完全な対極にあるんです。具体的には、以下のような点がADHDの特性とマッチする可能性があります。
- タスクが明確(シングルタスク): 「この部屋のゴミを集める」「この床を拭く」と、やることがハッキリしています。
- 割り込みが少ない: 基本的に自分のペースで黙々と作業を進められます。電話や上司の指示で頻繁に作業が中断されることが少ないです。
- 対人ストレスが少ない: 複雑な人間関係や「空気を読む」コミュニケーションが最小限で済みます。
- 体を動かせる: じっと座っているのが苦手な「多動性」の特性を、体を動かすことで発散できます。
もちろん、全ての清掃業が当てはまるわけではありませんが、特に不注意優勢型の方や、複雑な対人関係、曖昧な指示に疲弊した人にとって、現実的な選択肢の一つかもしれませんね。同じ理由で、「工場ライン工」「トラック運転手」「ポスティング」なども候補に挙がることがあります。
ADHD向いてる仕事2chの議論

「向いてない仕事」が分かったところで、今度は「じゃあ、どんな仕事なら?」という疑問を掘り下げます。ADHDの特性と呼ばれる「天才性」の正体や、フリーランスという働き方、そして私たちが使える「支援」について、2chの議論も踏まえながら整理しますね。
ADHDの特性と天才と呼ばれる理由
ADHDが「天才」と呼ばれることがあるのは、その能力の「凸凹(デコボコ)」が極端だからかなと思います。
思考があちこちに飛ぶからこそ生まれる「ユニークな発想力」や、興味のあることには寝食を忘れて没頭できる「過集中」。これが、研究や芸術、技術職などの専門分野で、他の人には真似できない高い成果を生み出すことがあります。
ただ、2ch的な本音で言えば、この「天才」性は、「興味のないことには1ミリも集中できない」「致命的なケアレスミスが多い」といった「ポンコツ」さと表裏一体です。
「天才」と「ポンコツ」の表裏一体
- 過集中: プログラミングに没頭して素晴らしいコードを書く(天才)が、その間トイレも食事も忘れ、別の重要なタスクを完全に忘却する(ポンコツ)。
- 発想力: 会議で誰も思いつかないアイデアを出す(天才)が、話が飛びすぎて何を言いたいのか伝わらず、議事を混乱させる(ポンコツ)。
この極端な落差こそが、ADHDの「天才」と呼ばれるゆえんであり、同時に「生きづらさ」の源泉でもあるんですね。
ADHD女性特有の仕事の悩み

ADHDの特性に性差はありませんが、女性は社会的な役割期待から、特有の困難を抱えがちです。
特に女性は、多動・衝動性が目立たず「不注意」が中心となる「不注意優勢型」が多い傾向が指摘されています。子どもの頃は「おとなしい子」「夢見がちな子」として見過ごされやすく、大きな問題を起こさない「良い子」だったために、診断されないまま社会人になるケースも少なくありません。
その結果、一般職(事務職)などで「なぜかミスが多い」「集中できない」「マルチタスクがこなせない」「片付けられない」といった困難に直面し、「他の女性はできているのに、なぜ自分だけできないんだろう」と、非常に強く自己肯定感を失いやすいです。
見えない疲弊「ソーシャル・カモフラージュ」
また、コミュニケーションが得意に見える女性当事者も多いです。しかし、それが実は、周囲の会話や期待に必死で合わせるための「過剰適応(ソーシャル・カモフラージュ)」であるケースも少なくありません。
職場では「普通」を装うために全エネルギーを使い果たし、帰宅した途端、一言も話せないほど「電池切れ」になってしまう…。こうした見えない疲弊も、女性特有の悩みとしてよく語られています。
ADHDグレーゾーンと使える支援

医師の診断基準は満たさないけれど、ADHDの特性(不注意、マルチタスクが苦手など)があって、職場環境とのミスマッチに苦しんでいる…いわゆる「発達障害のグレーゾーン」の方も多いと思います。
グレーゾーンの方は、「診断が出ないから支援の対象外だ」「自分の努力不足だ」と思い込み、一人で抱え込んでしまいがちです。
ですが、そんなことはありません。診断や障害者手帳がなくても無料で利用できる公的な就労支援機関があります。
診断がなくても相談できる場所
例えば、以下のような公的機関です。
診断なしで使える公的支援(例)
- サポステ(地域若者サポートステーション): 働くことに悩みを抱える15歳~49歳の方が対象です。(出典:厚生労働省「地域若者サポートステーション」)
- ジョブカフェ(若年者のためのワンストップサービスセンター): 主に若年層(おおむね34歳以下など、地域による)の就職支援をしています。
- ハローワーク(公共職業安定所): 全年齢対象。発達障害の特性に詳しい専門の相談窓口が設置されている場合もあります。
これらの機関では、診断の有無に関わらず、「今の仕事が合わない気がする」「どういう仕事を探せばいいか分からない」といったキャリア相談や就職活動の支援を無料で受けることが可能です。
利用条件や支援内容は地域によって異なる場合があるため、まずはお近くの機関の公式サイトを確認したり、電話で「診断はないのですが…」と問い合わせてみるのが良いかなと思います。
ADHDとフリーランスという選択肢

「もう会社員(組織)が無理!」という本音も、2chのADHDスレッドでは必ず登場するテーマです。厳格な時間管理や対人関係のストレス、マルチタスクの強制から解放される「フリーランス」は、非常に魅力的に見えますよね。
ただ、これは「両刃の剣」であり、最大の「罠」でもあると私は考えています。
メリットは、もちろん「自由度の高さ」です。自分の興味のある案件だけを選び、「過集中」を最大限に活かせます。苦手な会議や雑談も最小限にでき、働く時間や場所も自由です。
しかし、致命的なデメリットは、「自分で段取り、計画、経理を全てこなさなくてはならない」ことです。これ、まさに「事務」ですよね。
フリーランスの「罠」
例えば、プログラマーとして「コーディング(適職)」は完璧にできても、「請求書の作成・送付(事務)」を忘れたり、衝動性で受注しすぎてスケジュール管理が破綻したり、確定申告(経理)を先延ばしにしすぎてペナルティを受けたり…。
このように、「本業(適職)」以外の「管理業務(不適な事務)」で詰んでしまうリスクが常にあります。
ADHD当事者の方がフリーランスとして成功するには、自分の「事務」能力を過信せず、税理士さんやオンラインアシスタントを雇って苦手な作業を「外注」する覚悟を持つか、第3部で見たようなライフハックを駆使して徹底的な自己管理システムを構築するかの二択が求められるかなと思います。
ADHDが向いてる仕事・2ch検索の次の一歩

「adhdの向いてる仕事」を2chで検索し、情報を集めて「あるある!」「自分だけじゃなかった!」と共感することは、困難を乗り越えるための本当に大切な第一歩です。孤独感が和らぎますよね。
ただ、情報収集や共感だけでは、残念ながら「詰む」状況は解決しにくいのも事実です。
ADHD当事者の方が直面する困難は、「気合が足りない」といった個人の努力の問題ではなく、「脳の特性と環境のミスマッチ」という構造的な問題です。
一人で抱え込まないでください
「ミスばかりで働く自信がない」「仕事が続かない」と一人で抱え込んでいる場合、最も現実的で効果的な次の一手は、専門家の支援を「外部足場」として活用することです。
例えば「就労移行支援事業所」は、まさにそうした困難を抱える(診断のある)ADHD当事者をサポートするための機関です。専門家の助けを借りて、自分の特性を客観的に把握し、どんな環境なら強みが活き、どんな配慮が必要かを明確にできます。
就労移行支援のメリット(例)
- 自己理解: 専門家と面談し、自分の「得意」と「苦手」を客観的に整理できます。
- スキル習得: PCスキルや、タスク管理術、職場でのコミュニケーション術などを訓練できます。
- 就職活動支援: 自分の特性に合った求人を一緒に探し、面接対策などもサポートしてもらえます。
- 職場定着支援: これが最大のメリットの一つかも。就職後も支援員が定期的に面談し、「長く働き続けるため」のサポートを継続的に受けられます。
「adhdの向いてる仕事」を2chで探す孤独な戦いを終えて、医師や(診断がなくても使える)公的支援機関、あるいは(診断があるなら)就労移行支援事業所といった専門家に相談することは、恥ずかしいことでは全くありません。
それは「逃げ」ではなく、安定して働き、自分自身の能力を発揮するための、最も確実で、戦略的な一歩だと私は思います。
この記事は、特定の医療的アドバイスや診断を提供するものではありません。仕事や健康に関する深刻な悩みがある場合は、必ず医師やカウンセラー、公的な支援機関など、専門家にご相談ください。
人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)
発達障害ランキング






